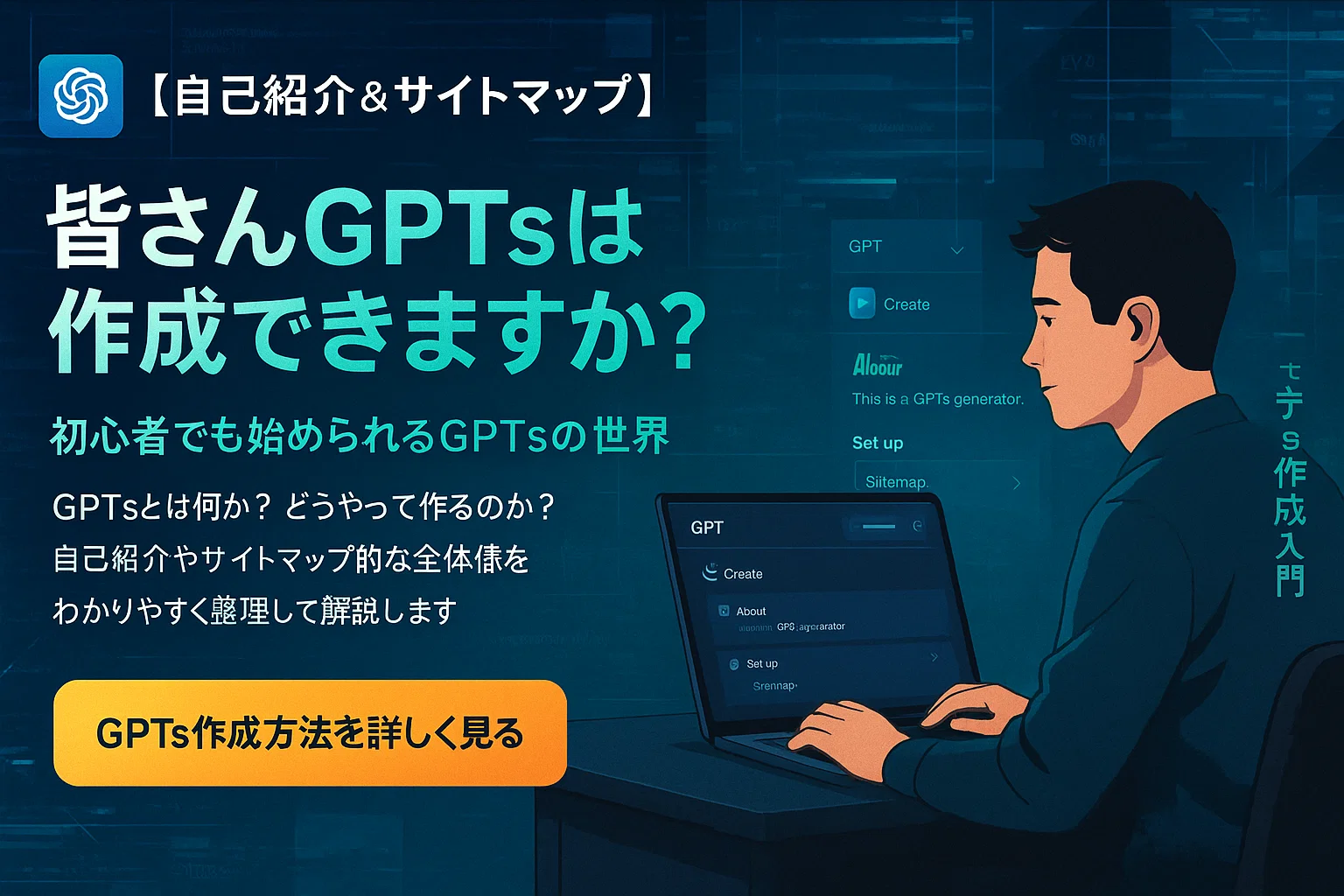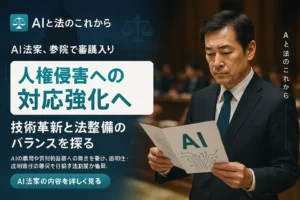はじめに
ChatGPTを使ったことがある方なら、「もっと特定の用途に特化したAIツールがあったらいいのに」と思ったことありませんか?
実は、GPTsという機能を使えば、誰でも簡単に自分専用のAIツールを作ることができるんです。
レシピ提案AI、記事作成サポートAI、商品分析AIなど、アイデア次第で無限の可能性が広がります。
この記事では、GPTs作成の基礎から実際の手順、応用テクニックまで、初心者の方でも迷わず実践できるよう丁寧に解説していきますね。
GPTsとは何か?基礎知識を押さえよう
GPTsの定義と基本的な仕組み
GPTsって聞いたことあるけど、実際どんなものか案外知らない方も多いんじゃないでしょうか。
簡単に言うと、ChatGPTをカスタマイズして、特定の目的に特化したAIツールを作る機能のことなんです。
通常のChatGPTは「何でも屋さん」みたいな存在で、質問すればなんでも答えてくれますよね。
でもGPTsは、その万能なChatGPTに「○○だけを専門的にやってほしい」という指示を事前に組み込んで、特定分野のプロフェッショナルAIに変身させる仕組みなんです。
たとえば、料理が苦手な方向けに「冷蔵庫の食材写真を送るだけで、その日の献立を提案してくれるAI」を作ったり、ブログを書いている方向けに「記事のタイトルを入力するだけで、構成案を自動生成してくれるAI」を作ったりできるわけです。
なぜGPTsが注目されているのか
最近GPTsがこんなに話題になっているのには、いくつか理由があったりします。
まず一つ目は、プログラミング知識が一切不要だということ。従来、こういったカスタムAIツールを作ろうと思ったら、プログラミングスキルが必須でした。
でもGPTsなら、普通の文章で指示を書くだけで、誰でも作れちゃうんです。
二つ目は、作成コストがほぼゼロだということ。
ChatGPTのPlusプラン(月額20ドル)に入っていれば、追加料金なしで無制限にGPTsを作成できます。
これまでカスタムAIツールを外注すると数十万円かかることもありましたが、GPTsなら自分で気軽に作れるんですね。
三つ目は、実用性の高さです。
単なる実験的なツールではなく、実際のビジネスや日常生活で使える本格的なAIツールが作れるんです。
実際に、副業で使える商品分析AIや、時短に役立つ業務効率化AIなど、多くの人が実用的なGPTsを作って活用しています。
GPTsでできることの範囲
GPTsで作れるAIツールの種類は、本当に幅広いんです。
ここで主要なカテゴリーを整理してみますね。
コンテンツ制作系では、記事の構成案作成、SNS投稿文の自動生成、メール文面の作成支援、プレゼン資料の構成案作成などができます。
特にライターやマーケターの方には重宝されているみたいですね。
ビジネス支援系では、商品の競合分析、市場リサーチの自動化、顧客対応の自動化、業務プロセスの最適化提案などが可能です。小規模事業者の方でも、まるで専属コンサルタントがいるような感覚で使えたりします。
教育・学習系では、個別指導型の学習支援、語学練習のパートナー、資格試験の対策支援、技術的な質問への専門回答などができます。自分のペースで学習を進めたい方には特に便利ですよね。
日常生活支援系では、先ほど紹介したレシピ提案や、旅行プランの作成、家計管理のアドバイス、健康管理のサポートなどができます。毎日の小さな悩みを解決してくれる頼もしい存在になってくれます。
GPTsの種類と特徴を理解しよう
用途別GPTsの分類
GPTsは用途によっていくつかのタイプに分けることができるんです。
まず分析・診断型は、データや情報を分析して結果を提示するタイプです。
商品レビューの分析、文章の添削、画像の内容説明などがこれに当たります。
生成・制作型は、新しいコンテンツを作り出すタイプですね。記事作成、デザインアイデアの提案、楽曲の作詞などができます。クリエイティブな作業をサポートしてくれる頼もしい相棒になってくれます。
対話・相談型は、ユーザーとの対話を通して問題解決をサポートするタイプです。カウンセリング、学習指導、技術サポートなどが該当します。まるで専門家と話しているような感覚で相談できるのが魅力ですね。
自動化・効率化型は、定型的な作業を自動化してくれるタイプです。メール文面の生成、スケジュール管理、データ整理などができます。時間のかかる単純作業から解放されるので、本当に重要な作業に集中できるようになります。
公開範囲による分類
GPTsは公開範囲によっても分類できるんです。
プライベート型は自分だけが使用できるGPTsで、個人的な業務効率化や趣味に活用します。
他人に見られたくない内容や、自分専用にカスタマイズしたい場合に選択します。
限定共有型は、特定のユーザーやチームとだけ共有するGPTsです。会社内での業務効率化ツールや、家族間での情報共有ツールなどに使われることが多いですね。
一般公開型は、誰でも使えるように公開するGPTsです。多くの人に役立つツールを作って社会貢献したい場合や、自分の作品を多くの人に使ってもらいたい場合に選択します。
GPTs作成の準備をしよう
必要なアカウントとプラン
GPTsを作るには、まずChatGPTのアカウントが必要になります。
ただし、ChatGPT Plusプラン(月額20ドル)への加入が必須なんです。
無料プランではGPTsの作成機能は使えないので、ここは投資だと思って加入することをおすすめします。
ChatGPT Plusプランに加入すると、GPTsの作成・使用が無制限になるだけでなく、最新のGPT-4モデルも使えるようになります。
また、ピーク時でも安定してサービスを利用できるので、本格的にAIツールを活用したい方には必須のプランだったりします。
加入手続きは案外簡単で、ChatGPTのサイトにログインして「Upgrade to Plus」ボタンをクリックし、クレジットカード情報を入力するだけです。すぐに使い始められるので、思い立ったらその日から始められますよ。
作成前の企画・設計
いきなりGPTsを作り始めるのではなく、まずは企画をしっかり練ることが成功の秘訣です。
「どんな人の、どんな悩みを、どうやって解決するのか」を明確にしておくと、後の作業がスムーズに進みます。
まずターゲットユーザーを具体的に設定しましょう。
「料理が苦手な一人暮らしの社会人」「副業でアフィリエイトを始めたばかりの主婦」「英語学習に挫折しがちな学生」など、できるだけ具体的にイメージすることが大切です。
次に解決したい課題を明確にします。
「毎日の献立を考えるのが面倒」「商品選びに時間がかかりすぎる」「英語の発音練習相手がいない」など、ユーザーが抱えている具体的な困りごとを特定します。
そしてGPTsが提供する価値を定義します。
「食材写真から30秒で献立提案」「商品の良い点・悪い点を客観的に分析」「24時間いつでも英語会話練習」など、ユーザーにとってのメリットを具体的に表現しましょう。
必要な素材・リソースの準備
GPTs作成に必要な素材も事前に準備しておくと作業が効率的に進みます。
プロンプト(指示文)は最も重要な要素で、GPTsの性格や機能を決定します。どんな口調で話すのか、どんな手順で作業を進めるのか、どんな形式で結果を出力するのかなどを詳細に記述します。
参考資料やサンプルデータも用意しておきましょう。
たとえばレシピ提案AIを作るなら、実際のレシピデータや栄養成分表を用意しておくと、より実用的なGPTsが作れます。
商品分析AIなら、分析項目のテンプレートや、過去の分析事例などがあると便利ですね。
アイコン画像も忘れずに準備しましょう。
GPTsには専用のアイコンを設定できるので、用途に合った分かりやすい画像を用意しておくと、後で見つけやすくなります。
無料の画像生成AIを使って作ることもできますし、シンプルなイラストなら自分で描いても大丈夫です。
STEP1:ChatGPTでGPTsビルダーを起動する
GPTsビルダーへのアクセス方法
それでは、実際にGPTsを作っていきましょう!
まずはChatGPTにログインして、画面左上の「Explore」メニューをクリックします。
すると「My GPTs」という項目が表示されるので、そこをクリックしてGPTs管理画面に移動します。
GPTs管理画面では、これまで作成したGPTsの一覧が表示されます。
初めての方は何も表示されないので、画面右上の「Create a GPT」ボタンをクリックしましょう。
これでGPTsビルダーが起動します。
GPTsビルダーには「Create」タブと「Configure」タブの2つがあります。
「Create」タブでは対話形式でGPTsを作成でき、「Configure」タブでは詳細設定を手動で行えます。
初めての方は「Create」タブから始めることをおすすめします。
初期設定の基本的な流れ
「Create」タブを開くと、GPT Builderという専用のAIが「どんなGPTを作りたいですか?」と聞いてきます。
ここで作りたいGPTsの概要を日本語で説明しましょう。
たとえば「料理の写真を送ると、その料理に合うワインを提案してくれるGPTを作りたいです」といった感じですね。
すると、GPT Builderが自動的に名前やアイコン、基本的な動作を提案してくれます。
この段階では完璧である必要はないので、「だいたいこんな感じかな」という程度で次に進んで大丈夫です。
後でいくらでも修正できますからね。
名前について聞かれたら、分かりやすくて覚えやすいものを選びましょう。
「ワインソムリエAI」「料理ペアリング先生」など、用途が一目で分かる名前がおすすめです。
あまり長すぎると覚えにくいので、10文字以内に収めるのがコツだったりします。
トラブルシューティング:よくある初期エラー
GPTsビルダーを初めて使う際に、いくつかよくあるエラーがあります。
「Create a GPT」ボタンが表示されない場合は、ChatGPT Plusプランに加入していない可能性が高いです。
プランを確認して、必要に応じてアップグレードしてください。
「Something went wrong」というエラーが表示される場合は、ブラウザのキャッシュをクリアするか、別のブラウザで試してみてください。ChromeやFirefoxなど、主要なブラウザであれば問題なく動作するはずです。
作成途中で画面が固まってしまう場合は、一度ページを更新してみてください。
GPTsビルダーは自動保存機能があるので、途中まで作成した内容は残っています。安心して作業を再開できますよ。
STEP2:基本情報とペルソナを設定する
GPTsの名前とアイコンの決定
GPTsの名前は、ユーザーが一番最初に目にする重要な要素です。
分かりやすさと親しみやすさのバランスを考えて決めましょう。
たとえば「レシピ先生」「英会話パートナー」「記事構成メーカー」など、機能が直感的に伝わる名前がおすすめです。
アイコンについては、GPT Builderが自動生成してくれることもありますが、自分で用意した画像をアップロードすることも可能です。
正方形で、512px×512px以上の解像度があると綺麗に表示されます。
色合いは明るめで、シンプルなデザインの方がユーザーに好まれる傾向がありますね。
名前とアイコンは後から変更できるので、最初は仮で設定しておいて、GPTsの機能が固まってから最終調整するのも良い方法です。実際に使ってみると「この名前だとちょっと分かりにくいかな」という発見もあったりします。
キャラクター設定とトーンの決定
GPTsの「性格」や「話し方」を決めるのも重要なポイントです。
親しみやすい関西弁で話すキャラクターにするのか、丁寧語で話すプロフェッショナルなキャラクターにするのか、用途とターゲットユーザーに合わせて決めましょう。
たとえば、料理初心者向けのGPTsなら「お料理って最初は難しそうに見えるけど、コツを掴めば案外簡単だったりするんですよ〜」といった優しく励ましてくれる口調が良いでしょう。
一方、ビジネス向けの分析ツールなら「データを基に客観的に分析いたします」といった信頼感のある口調が適しています。
キャラクター設定では、専門知識のレベルも重要です。
初心者向けなら専門用語を使わずに分かりやすく説明し、上級者向けなら詳細な技術的説明も含めるといった具合に、ターゲットに合わせて調整します。
専門知識と得意分野の定義
GPTsの専門分野を明確に定義することで、より精度の高い回答ができるようになります。
「料理全般が得意」よりも「和食の基本調理法と、食材の組み合わせに詳しい」といった具体的な設定の方が、実用的なアドバイスができるんです。
専門知識のレベルも設定しておきましょう。
「料理学校で学んだレベルの知識」「管理栄養士レベルの栄養知識」「ソムリエ資格相当のワイン知識」など、参考となる資格や経験を設定すると、一貫性のある回答ができるようになります。
逆に「知らないことは知らないと言う」という設定も大切です。
専門外の質問に対して無理に答えようとせず、「その分野は専門外なので、詳しい方に相談することをおすすめします」と正直に答える設定にしておくと、ユーザーからの信頼度が上がります。
STEP3:指示(プロンプト)を詳細に作成する
効果的なプロンプトの書き方
プロンプトはGPTsの「脳」にあたる最も重要な部分です。
ここでGPTsの動作を詳細に指定することで、期待通りの結果を得ることができます。
まず基本的な役割から明確に定義しましょう。
「あなたは○○の専門家として、ユーザーの△△をサポートします」といった形で、GPTsの立ち位置を明確にします。
その後、具体的な動作手順を箇条書きで記述していきます。
「1. ユーザーの入力を分析する、2. 専門知識を基に最適な提案を考える、3. 分かりやすい形で結果を提示する」といった流れですね。
重要なのは、可能な限り具体的に書くということです。
「親切に答える」ではなく「専門用語は使わず、具体例を交えて、励ましの言葉も含めながら答える」といった具体的な指示の方が、期待通りの動作をしてくれます。
出力形式の指定方法
ユーザーにとって見やすく、使いやすい出力形式を指定することも重要です。
「回答は必ず以下の形式で出力してください」として、テンプレートを用意しておくと統一感のある結果が得られます。
たとえばレシピ提案なら「# 今日のおすすめ料理\n## 材料(2人分)\n- 材料1: 分量\n- 材料2: 分量\n## 作り方\n1. 手順1\n2. 手順2\n## ワンポイントアドバイス\n○○」といったテンプレートを指定します。
箇条書き、表形式、段落形式など、情報の種類に応じて最適な形式を選びましょう。
数値データなら表形式、手順説明なら箇条書き、概要説明なら段落形式といった具合ですね。ユーザーが情報を素早く理解できることを最優先に考えます。
制約条件と禁止事項の設定
GPTsが不適切な動作をしないよう、制約条件と禁止事項も明確に設定しておきましょう。
「医療アドバイスは絶対に行わない」「個人情報の収集は行わない」「違法な内容には一切関与しない」など、守るべきルールを明記します。
文字数制限や回答時間の目安も設定できます。
「回答は500文字以内で簡潔に」「複雑な分析が必要な場合は、まず概要を伝えてから詳細分析を行う」といった指示で、ユーザビリティを向上させることができます。
また、「分からない場合は推測で答えずに、追加情報を求める」「不確実な情報には必ず『参考程度に』などの注意書きを付ける」といった、信頼性を保つための指示も重要です。
STEP4:知識ベースとファイルのアップロード
参考資料の準備と整理
GPTsをより専門性の高いツールにするために、参考資料をアップロードすることができます。
まずは用途に応じて必要な資料を整理しましょう。
レシピ提案なら料理のレシピ集、商品分析なら分析手法のマニュアル、学習支援なら教材の要約などですね。
ファイル形式はPDF、Word文書、テキストファイル、CSV、画像ファイルなど多様な形式に対応しています。
ただし、ファイルサイズには制限があるので、必要な情報を精選してアップロードすることが大切です。
アップロードする前に、ファイルの内容を整理しておくことをおすすめします。
目次を作成したり、重要な部分にハイライトを付けたりしておくと、GPTsがより効率的に情報を活用できるようになります。
効果的な知識の構造化
単純にファイルをアップロードするだけでなく、知識を構造化して整理することで、GPTsの回答精度が大幅に向上します。
関連する情報同士をグループ化し、階層構造を作って整理しましょう。
たとえば料理関連なら「基本調理法 > 和食 > 煮物 > 肉じゃが」といった階層構造で情報を整理します。
これにより、ユーザーの質問に対して、より的確な情報を素早く見つけることができるようになります。
タグ付けも効果的な手法です。
各情報に「初心者向け」「時短レシピ」「節約料理」といったタグを付けることで、ユーザーのニーズに応じた情報検索が可能になります。
ファイルアップロード時の注意点
ファイルをアップロードする際には、いくつか注意すべき点があります。まず著作権の問題です。他人が作成した資料をそのままアップロードすることは避け、自分で作成した資料や、利用許可を得た資料のみを使用しましょう。
個人情報の扱いにも注意が必要です。顧客情報や個人の連絡先などが含まれた資料は、絶対にアップロードしないでください。GPTsは他のユーザーからアクセスされる可能性があるため、機密情報の漏洩リスクがあります。
ファイルの品質も重要です。文字化けしているファイルや、画質の悪い画像ファイルをアップロードしても、GPTsが正しく読み取れない場合があります。事前にファイルの内容を確認し、必要に応じて修正してからアップロードしましょう。
STEP5:テストと動作確認を行う
基本機能のテスト方法
GPTsの基本設定が完了したら、実際に動作確認を行いましょう。まずは簡単な質問から始めて、期待通りの回答が得られるかチェックします。想定している典型的な使用パターンを複数用意して、それぞれテストしてみてください。
テスト時には、回答の内容だけでなく、回答の形式、文章の長さ、口調なども確認しましょう。設定したキャラクターや出力形式通りに動作しているかをチェックします。期待と異なる部分があれば、プロンプトを調整して再テストします。
エラーケースのテストも忘れずに行いましょう。意図しない質問や、答えられない質問をした場合に、適切に対応できるかを確認します。「その質問にはお答えできません」といった適切な断り方ができているかもチェックポイントです。
問題点の特定と修正
テスト中に問題が見つかった場合は、原因を特定して修正していきます。回答が的外れな場合は、プロンプトの指示が曖昧すぎる可能性があります。より具体的で明確な指示に修正しましょう。
回答が長すぎる、または短すぎる場合は、文字数制限や回答の詳細度について調整が必要です。「簡潔に答える」「詳しく説明する」といった指示を追加したり、具体的な文字数制限を設けたりします。
口調や文体が期待と異なる場合は、キャラクター設定の部分を見直します。「親しみやすい関西弁で」「丁寧語で専門的に」といった指示をより詳細に記述することで改善できることが多いです。
パフォーマンスの最適化
GPTsの応答速度や精度を向上させるための最適化も重要です。プロンプトが長すぎると処理に時間がかかる場合があるので、不要な部分を削除して簡潔にまとめましょう。
アップロードした参考資料が多すぎると、関連する情報を見つけるのに時間がかかることがあります。本当に必要な資料のみに絞り込むか、資料の構造をより分かりやすく整理することで改善できます。
複雑な処理を要求している場合は、処理を段階的に分割することも効果的です。「まず概要を説明してから、詳細に入る」といった段階的なアプローチで、ユーザーにとって分かりやすく、システムにとっても処理しやすい構造にします。
応用テクニック:GPTsをさらに便利にするコツ
効率を上げる実践的なアドバイス
GPTsを作成する際の効率を上げるコツをいくつか紹介しますね。
まず、テンプレート化という手法があります。
よく使うプロンプトの構造をテンプレートとして保存しておけば、新しいGPTsを作る際に流用できて時間短縮になります。
段階的改善のアプローチも効果的です。最初から完璧を目指さず、基本機能だけを実装してリリースし、ユーザーからのフィードバックを基に少しずつ改善していく方法です。実際に使ってみると見えてくる改善点も多いので、この方法は特におすすめですね。
コミュニティの活用も大切です。GPTs作成者のコミュニティやフォーラムに参加して、他の作成者と情報交換することで、新しいアイデアや解決策を得ることができます。一人で悩むよりも、みんなで知恵を出し合った方が良いGPTsが作れたりします。
バージョン管理の概念も取り入れましょう。重要な変更を行う前には、現在の設定をメモしておいて、問題があった場合に元に戻せるようにしておきます。特にプロンプトの大幅な変更を行う際には、バックアップを取っておくことをおすすめします。
高度な機能の活用方法
GPTsには、基本機能以外にも便利な高度機能がいくつかあります。
カスタムアクション機能を使えば、外部のAPIと連携して、より複雑な処理を実行することができます。
たとえば、天気予報APIと連携して最新の気象情報を取得したり、翻訳APIと連携して多言語対応を実現したりできるんです。
Code Interpreter機能を活用すれば、データ分析やグラフ作成なども可能になります。CSVファイルをアップロードして統計分析を行ったり、データを可視化したグラフを自動生成したりできます。特にビジネス用途のGPTsでは重宝する機能ですね。
Browse with Bing機能を有効にすれば、最新の情報をリアルタイムで検索して回答に反映することができます。ニュース関連のGPTsや、時事情報を扱うGPTsには必須の機能です。
DALL-E機能を組み込めば、画像生成も可能になります。レシピ提案と合わせて料理の画像を生成したり、説明用の図解を自動作成したりできるので、視覚的にも分かりやすいGPTsが作れます。
よくある失敗とその対処法
GPTs作成でよくある失敗パターンと、その対処法もご紹介しておきますね。
過度に複雑化してしまうのは初心者によくある失敗です。あれもこれもと機能を詰め込みすぎて、結果的に使いにくいGPTsになってしまうケースです。対処法としては、「一つのGPTsには一つの主要機能」という原則を守ることです。シンプルで分かりやすいGPTsの方が、ユーザーに愛用されやすいんです。
ターゲットユーザーを意識しないのも失敗の原因になります。「誰でも使える万能ツール」を目指すあまり、結果的に誰の役にも立たないGPTsになってしまうことがあります。最初から明確にターゲットを絞り込んで、その人たちの具体的な課題を解決することに集中しましょう。
テストが不十分で公開してしまうのも危険です。自分だけでテストしていると、他の人が使った時に予想外の動作をすることがあります。可能であれば、身近な人に実際に使ってもらって、フィードバックをもらうことをおすすめします。
アップデートを怠るのも長期的には問題になります。GPTsは一度作って終わりではなく、ユーザーの要望や技術の進歩に合わせて継続的に改善していく必要があります。定期的に使用状況をチェックして、改善点があれば積極的にアップデートしていきましょう。
プロンプトの秘密主義も考えものです。他の作成者の作品を参考にして学ぶことで、自分のスキルも向上します。コミュニティで情報共有することで、みんなでGPTsの品質を向上させていけるはずです。
まとめ
GPTsの作成は、最初は難しそうに見えるかもしれませんが、実際にやってみると案外シンプルで楽しい作業だったりします。
基礎知識の理解から始まって、準備、作成、テスト、改善という流れを一つずつ丁寧に進めていけば、誰でも実用的なAIツールを作ることができるんです。
重要なのは、完璧を目指さずに「まずは作ってみる」という気持ちで始めることですね。
最初はシンプルな機能から始めて、使いながら少しずつ改善していく方法が結果的に良いGPTsを作る近道になります。
今回ご紹介した手順やコツを参考に、ぜひあなたも自分だけのGPTsを作ってみてくださいね。
きっと日常生活や仕事の効率化に役立つ、頼もしいAIパートナーが誕生するはずです。うまくいったらぜひ教えてくださいね!